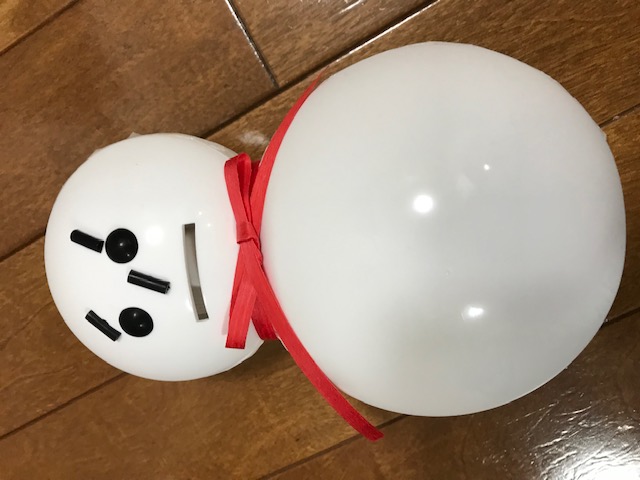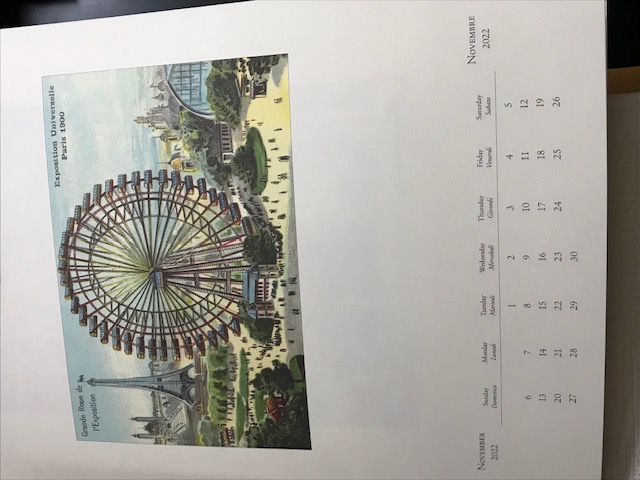初めて足を運ぶ土地で、道の駅や、直売所に足を運ぶ。
これはとても楽しいリサーチであり、ミニイベントだ。
珍しい地元ならではの農作物に出会えたりする。
デパートや大型スーパーに並ぶ、カタチやサイズの整った
キレイな野菜よりも、
近所の農家さんがそのまま持ち込んできたような、
ちょっと土がついたままだったり、
形が不格好だったりする野菜の方が、断然愛着がわく。
また、普段売り場で見たことのない野菜をみつけると、
思わず購入してしまう。
「何?これ?」
世の中には、まだまだ知らないものがたくさんある。
大量に流通する世界では出会えない、小さな発見が直売所には存在する。
さらに、親世代の人たちが、よく食していたであろうものに出会うと、
なぜか懐かしくなってしまう。
貧しい時代に食していたものたち。ちょっと面倒ではあるが、
ちゃんと美味しく食べられるものたち。
たまたま、「いものつる」をみつけた。
芋づる式とはここから来ているのかどうかわからないが、
畑の様子を、想像するのが楽しい。(といいつつ、土いじりは苦手であるが・・・)
食べるには水にさらしたり、皮をむいたりと面倒ではあるが、
なぜか、しみじみとした気持ちになる。日頃の疲れも吹っ飛ぶのが不思議だ。
「あのさ、これ、どうやって食べてた?」
「へえ、きんぴらにするの?」
「ちょっと、めんどうくさいよね」
と、手を動かしながら、ひとりで話している。
そう、母に話しかけているのだ。
きっと彼女はこういった類の野菜に親しんでいたはずだから。
扱い方は聞いても返事はないため、ネットで調べるが、
とにかく対話をするのが、いい。
野菜を切りながら、皮をむきながら、母に声をかける。
きっと、これからもそうするんだろう。
野菜ダイアローグは、自分にとって一種の癒しでもある。
そんなひととき、悪くない。
ちなみに、写真の野菜ははじめて出会ったもの。
コールラビと呼ぶらしい。
母は知っていたかな。そんなことで野菜ダイアローグを楽しむのも
四季の歓び。
大地の恵みを、母の思い出とともに、ありがたくいただく。