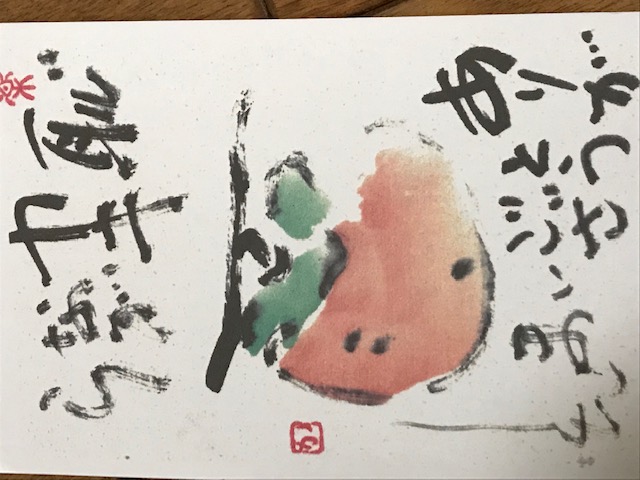実際に会うこともなく、ひとつのチームが3か月、自分たちで立てた計画のもとに、オンラインでミーティングを重ね、チームプランニングをして、プレゼンに臨んだ。そのチームは全部で5チーム。全国から集まった印刷女子30名。
その工程を上司たちもフルサポート。約50名で手探りで進んできた研修プログラム。
一緒にひとつのことを成し遂げた。
この余韻が消えないうちに、プレゼン大会の後、クロージングミーティングと
して取り組んだチームごとに、再びオンラインで集まった。
「お疲れ様でした!」と、それぞれの努力をねぎらい、そしてプレゼンについて自分たちのチームの振り返りと、他のチームの感想などをお互いに述べ合う。
今回行った研修は、チームプランニング&プレゼンがメインテーマであるが、
プレゼンをよく聴き、次に生かす。というところも大切なポイント。
当日、他のプレゼンをどう受け止め、いいところをみつけられたか、そしてその中で、自分たちのことはどうであったか?
客観的にみつめることは、とても重要だ。
やったことのない、大きな仕事をやったという自信。
オンラインプレゼンははじめてやった。でもこれでわかった。
これから、自信をもってできそう。いろんな意見が出てくる。
コロナでなければ、思いつくこともなかったこの挑戦。
皆さん、本当に大変であったけれど、やってよかったと口々に言われ、
こちらもほっとする。
オンラインで出会い、生まれ、育まれた関係。
研修が終わったから、チームも解散。はい、お疲れ様!
では終わりたくない。
また、オンラインで培ったこそ、さまざまな配慮のもとで
丁寧に育んだ関係であるため、絆は深い。
ここで、終わりではなく、ここから新たに何かできるかも?
という次の希望も見えてきた。
オンラインから生まれた関係。どうかここで終わらせず
リアルにつなげたい。
コロナが終わったら、ぜひ会いましょう。
もっと、何かしていきませんか?
そんな思いを込めて、クロージングミーティングを終える。
オンラインは、何とも言えない余韻を残すものだ・・。
とにかく、皆さんの奮闘ぶりに頭が下がり、こちらが感動した。
どんな環境でも逃げずに前に進むと、
必ず、いいことがある。