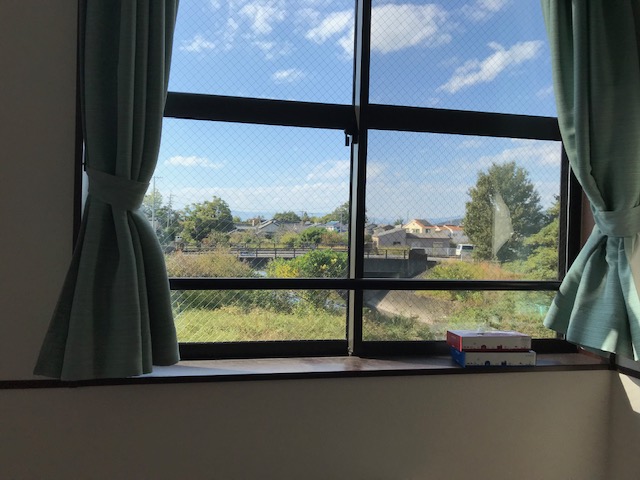両親が健在だった頃、家族でよく利用していた和食レストランがある。
久しぶりに、妹と二人で店をたずねる。
たまたまかかってきた電話で訃報を突然知って、驚き悲しんでおられたため、
気になって、元気な顔を見せるためランチに行くことにした。
事情を把握しているママさんは、突然の来店にこれまたびっくりされ、
改めて、両親の元気だった頃のこと、本当にお世話になった、いろんな
お客さんを連れてきてくれた・・と涙ながらに哀悼と感謝の言葉を
かけてくださった。
そこへ、何も知らないスタッフのおばちゃんが、お茶を運んできて
「お父さん、元気?」
と笑顔で、いつもどおり尋ねてきた。
「いえ、私たちは元気なんですけど・・・」
と切り出すと絶句され、まさか・・・と驚かれ、気遣いの言葉をいただいた。
両親がいかにこの店を愛用していたか、いろんな話をしながら
妹とこの1か月を振り返り、食事をした。
いつも、両親と一緒に来て、どんなに夫婦喧嘩をしていてもここに
来ると元通りになって・・・と、そんなこともくっきりと思い出した。
母がいつも団体の会食を予約していたが、コロナでそんな団体客もばったり。
そんななか、この年末に向け、母の代わりに仲間の方が30名の会食を
予約してくれたとママが感謝。
「おかあちゃん、天国へ行っても、店のこと心配してくれているんだわ」
そんな会話から、母が世話好きであったことも思い出す。
「お父ちゃんに、生ビールでもと思ったけどサーバの調子がよくないわ。
日本酒なら持って行けるね。時々日本酒も飲んでたしね」
と言って、ママは、私たちが食事をしているテーブルに、父用のお酒を
用意しようとされた。
亡き父へのおもてなしだ。
そして、帰り際に瓶入りの日本酒と、それとは違うものが入ったビニル袋を
厨房からもってきて、私たちに手渡す。
「これ、お父ちゃんとお母ちゃんに。お父ちゃん、カレイの煮つけが好きやったから、二人分。お父ちゃんとお母ちゃんに、あげて」
なんと、父の好物だった魚の煮付けをつくってくれたのだ。
確かに、ここに来ると、いつも必ず注文していた。
煮付けの汁がこぼれないようにそっと持ち運びながら、家族でこの店に通い、
父と乾杯し、ささやかな家族コミュニケーションを楽しんでいた頃を思い出す。空の上から、父は晩酌をしながら、母がしゃべり続けるのと、そうかそうかと
喜んできいていることだろう。
馴染であったお店に、こんな風にもてなしていただけて、本当に父も母も喜んでいることだろう。
幸せな時間を送っていることだろう。とあれこれ想像する。
空の上で、カンパイ。ほんとうに、長い人生、お疲れ様でした。
カレイの味が、なんだかしみじみ・・・。