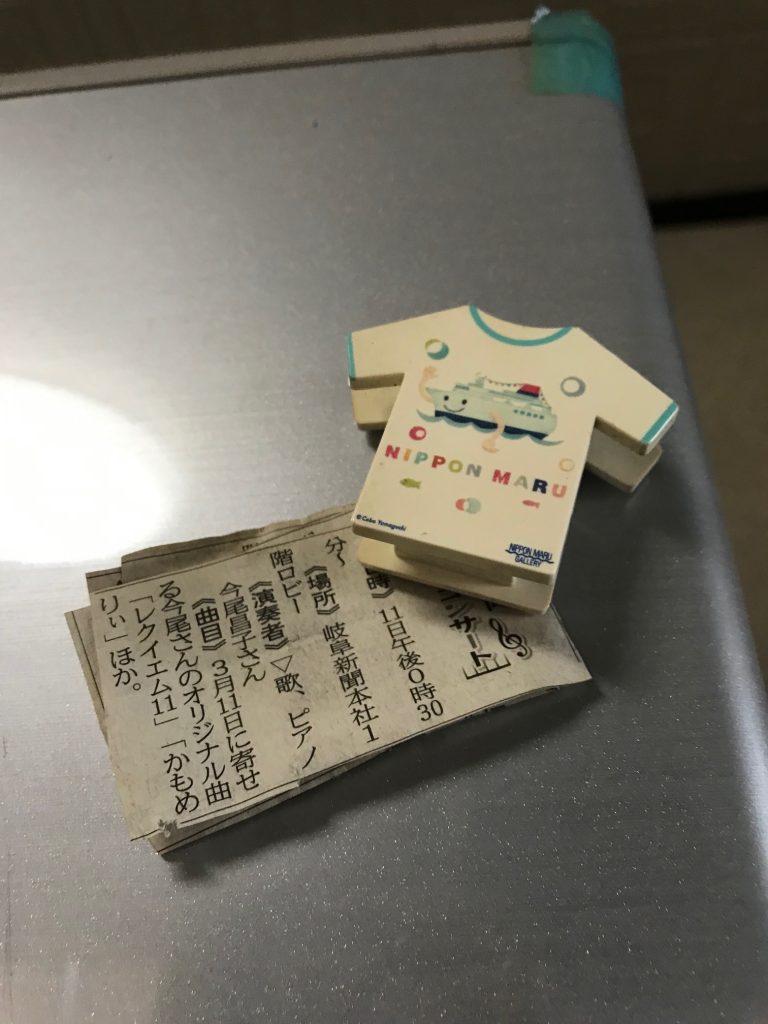ネット社会の影響か、ひとりで画面に向かって過ごす時間が増えていることの弊害か、最近では、カフェやファーストフードや電車の中で、電話に出る人が増えている。少なくとも、最近自分が行く場所ではそんな光景をよく目に耳にする。
年配の方なら、まあ、お年寄りなので、仕方ないか~と思うことも多かったが、最近では若い人が、平気でそんな行動、会話をしているので、驚き、がっかりする。
先日も、20代ぐらいの男性がファーストフード店内で、WEB会議をしていて、さすがに驚いた。なぜこんな公的な場所で、そんな行為ができるのだろう。
以前、電車の中で化粧をする若い女性を見て、これも驚いたが、これはまだ
こちらが視界から外れれば、まあ、見えなくなる。
でも、通話の大きな声が店内に響くと・・・。
お店も、電車も、公的空間だ。
しっかり企業側も、お客に注意喚起をしなければならない。というのも
情けない話だ。接客業で、お客様に注意をするのは、なかなかむつかしい。
ハードルが高い。対応力がないと、トラブルになることもある。
もうかなり昔の話。携帯が海外で少しづつ普及し始めた頃。上海や香港の地下鉄内で、大きな声で携帯で話す人達を見て、マナーがないな。日本は、本当に
いい国だと。と思った四半世紀前。
ネット社会の普及は、公私をボーダレスにしている。
これは、人の迷惑を考えない、と言う悲しい現実でもある。
ジャパンプライド。ある企業が掲げている言葉であるが、
日本人のコミュニケ―ション意識、エチケット面もジャパンプライドを
保ってほしい。
若い人は、今、どこで教育を受けているのだろう?
ふと気になる。
相手によっては、近所のおばちゃん風でつい口を出したくなる昨今。
ふと、母がそんなことを嘆いたことを、思い出した。