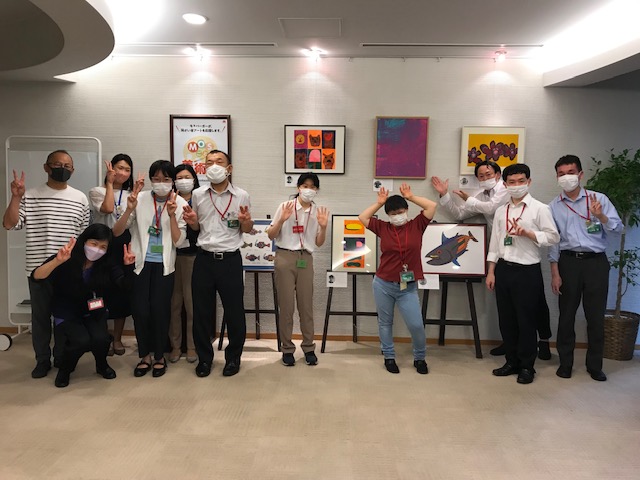両親が旅立ってから、よく花を買うようになった。
祈り、お供えというだけでなく、自分の癒しのためにである。
常に何かちょっと飾ってみる。
くらしのなかのオアシスだ。
バラがシンボルのデパートの花売り場の前を通ったら
「今日はローズの日」ということで、バラを安価に提供
していた。1本売りも安くしてくれるようだ。
そこで目に飛び込んできたのが
このオレンジのバラ。名前は「ミルバ」である。
もしかして、あのイタリアの歌手が由来?そうミルバは
先日もここに書いたが、母と同じく昨年亡くなったイタリアの
歌手。まさに情熱と愛の歌い手。
確かにこのバラも情熱を感じる色だ。
早速1本買ってみる。
きれいなオレンジ。レトロな色合いと感じる人もいるかも
しれないが、私はこの1本から生命を感じる。
真っ赤な赤とは違う、炎のような生きる力・・・。
花言葉を調べてみると、
「今この瞬間を生きる」という意味だそうで、まさに
今の自分にピッタリの言葉であり、見ていて元気も沸いて
くる。
あのつややかな伸びある声のミルバのことを思い出しながら、
私も今という瞬間を
精いっぱい生きていこうと改めて心に決める。
バラには、実にいろんな種類がある。
ぜひいろいろ試して、それぞれの思いに包まれ、
できる限り、美しく年を重ねたい。
ミルバなラビアンローズを!生き続けたい。